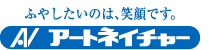監修者一覧
亜鉛は私たちの体にさまざまな効果をもたらしてくれる栄養素です。日々の食事やサプリで亜鉛の摂取を意識している人もいるのではないでしょうか。
この記事では亜鉛の効果や亜鉛サプリを飲むタイミングなどについて解説します。「亜鉛は薄毛予防の効果が期待できる?」、「亜鉛サプリを飲むタイミングはいつ?」といった情報が知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
亜鉛とは?

まずは亜鉛の基本情報や効果を解説します。亜鉛の幅広い働きを知り、なぜ人の体に欠かせないのかを理解しておきましょう。
亜鉛とは、私たちの体の中にある身近な栄養素
(出典:(1)亜鉛)
(出典:(2)日本人における亜鉛摂取量の現状と摂取基準)
(出典:(3)亜鉛 – 「 健康食品 」の安全性・有効性情報)
亜鉛は必須ミネラルと呼ばれる栄養素のひとつで、さまざまな働きがあります。亜鉛の主な働きは、以下のとおりです。
・酵素の構成や酵素反応の活性化
・ホルモンの合成や分泌の調節
・免疫反応の調節
・タンパク質やDNAの合成
近年の日本人は亜鉛が不足傾向にあることがわかっています。厚生省は成人男性10mg・成人女性8mgを1日の摂取目安としていますが、日本人の平均的な1日の亜鉛摂取量は9mgに届かず、若い女性は6.5mg程度です。加工食品を食べる機会が多くなり、食品添加物の影響で亜鉛の吸収率も下がっていると推察されています。
日本人の亜鉛不足はさまざまな健康リスクがあるだけでなく、日本人男性の生殖機能低下の一因である可能性も指摘されています。
味覚を正常に保つ
(出典:(4)低亜鉛血症を伴う味覚障害患者に対する酢酸亜鉛水和物製剤投与に関する検討)
私たちは舌表面に多くある「味蕾(みらい)」という器官で味を感じます。
亜鉛の欠乏により味蕾細胞の入れ替わり時間の延長、構造・形態の異常が生じて、機能低下を起こすことが知られています。味覚障害は亜鉛欠乏症の症状のひとつで、唯一エビデンスのある治療は亜鉛補充療法です。
味覚障害で味がわからなくなると、食事をおいしく感じられなくなり、食欲低下や発育障害などの症状を引き起こす場合があります。
抗酸化作用
(出典:(5)酸化ストレスと抗酸化療法)
体内で発生した活性酸素は、多くの疾患の発症や悪化につながるとされています。よく知られているものとしては、老化、動脈硬化、肝障害、虚血再環流障害、糖尿病、白血病、肺気腫、アレルギー疾患、がんなどが挙げられます。
活性酸素の発生を抑制するためには、抗酸化物質と呼ばれる酵素が必要です。抗酸化物質はたんぱく質といくつかの金属から合成されており、亜鉛も必須成分のひとつです。
免疫力の向上
(出典:(6)免疫システムの概要)(出典:(7)亜鉛)
亜鉛は細菌やウイルスから体を守る免疫細胞を正常に機能させるためにも、必要とされる栄養素です。
亜鉛不足により免疫力が下がることや、さまざまな病原体に対する感受性が強くなることが知られています。
また亜鉛は鼻の粘膜内でウイルスの動きを直接阻害し、炎症を抑えることによって、風邪症状の期間を短縮・重症度を軽減できると考えられています。
発育や成長
(出典:(8)亜鉛)(出典:(9)亜鉛欠乏症の診療指針2018)
亜鉛は体の発育や成長、発達にも重要な栄養素です。
亜鉛の欠乏によって成長ホルモンの分泌が減少するため、とくに子どもの場合は、低身長症や体重増加不良などの発育障害につながります。男児の場合は性腺機能の発達にも影響を及ぼします。正常な発育を促すためには、十分な亜鉛の摂取は欠かせません。
髪の毛や皮膚の健康維持
(出典:(10)毛包と表皮の形成における亜鉛の役割を解明)(出典:(11)やっと表舞台に立てた金属一 亜鉛一)
亜鉛は髪の毛や皮膚の健康維持にも必要不可欠です。亜鉛が不足すると髪の毛や皮膚の形成に支障をきたし、皮膚炎や脱毛といった症状につながります。
体内に存在する亜鉛のうち、約20%は髪の毛や皮膚といった上皮組織に存在しており、不足により症状が出やすいことが知られています。
生殖機能の維持や改善
(出典:(12)亜鉛と生殖)
男性の前立腺と精巣には、高濃度の亜鉛が含まれています。そのため皮膚や髪と同様に、亜鉛不足の影響が出やすい臓器といえます。
亜鉛はテストステロンの合成や精子の形成などに関わる栄養素です。亜鉛が不足すると精巣での精子形成が阻害され、精子数の減少や血中のテストステロン濃度の低下、さらに精巣の萎縮などを誘発します。
精神の安定
(出典:(13)タンパク質と脳の栄養~うつ病とタンパク摂取~)(出典:(14)抑うつ症状とミネラル摂取との関係―断面調査の結果から―)
ある研究では亜鉛などのミネラルを多く摂取している人は、摂取が少ない人に比べて抑うつ症状が少ないことがわかっています。また亜鉛などのミネラルは「セロトニン」などの脳神経伝達物質の合成にも関わっています。
「セロトニン」はうつ病の治療薬にも利用されている成分です。うつ症状のある患者はセロトニン値が低いことがわかっています。
そのためセロトニンの原料であるタンパク質と、セロトニンの合成に関わるミネラルを多く摂取することは、うつ症状の緩和、精神的な安定につながると考えられています。
亜鉛が不足するとどうなる?
(出典:(15)亜鉛欠乏症の診療指針 2018)
亜鉛が不足すると、以下のような不調が現れることがあります。
- 味覚異常
- 皮膚炎
- 脱毛
- 貧血
- 口内炎
- 下痢
- 男性性腺機能異常
- 易感染症 (感染しやすい状態)
- 創傷治癒遅延 (傷が治りにくい)
- 小児発育障害
亜鉛欠乏症になる人は増加傾向にあり、珍しい病気ではなくなってきていることが指摘されています。
亜鉛を多く含む食材

(出典:(16)亜鉛 – 「 健康食品 」の安全性・有効性情報)(出典:(17)日本食品標準成分表 魚介類)(出典:(18)日本食品標準成分表 豆類)(出典:(19)日本食品標準成分表 野菜類)(出典:(20)米の亜鉛の栄養有効性の化学的・系統的解析)(出典:(21)穀類)(出典:(22)大豆発酵食品による亜鉛栄養改善の可能性)(出典:(23)日本型食生活の栄養学的検討(1))
亜鉛はさまざまな食品に含まれています。とくに亜鉛を多く含む食材は下表のとおりです。いずれの数値も「可食部100g当たりの成分量(mg)」を示しています。
動物性の食材
| 牡蠣 養殖 生 | 14.0 |
| 輸入牛もも 焼き | 6.6 |
| うなぎの蒲焼き | 2.7 |
| まあじ 皮付き 生 | 1.1 |
| さば 生 | 1.1 |
植物性の食材
| カシューナッツ フライ味付け | 5.4 |
| きなこ 全粒大豆 黄大豆 | 4.1 |
| アーモンド フライ味付け | 3.1 |
| 糸引き納豆 | 1.9 |
| えだまめ 生 | 1.4 |
また亜鉛は日本人になじみの深い米や味噌からも摂取できます。
米の亜鉛量は、乾燥重量100gあたり1.96±0.20mgです。米を炊くと一緒に入れた水を吸って膨らみ、乾燥重量65gで茶碗に中盛り1杯150gのごはんになります。日常の摂取量から考えると、米は亜鉛の重要な供給源であることがわかります。
味噌の原料である大豆には、亜鉛の吸収を妨げるフィチン酸も多く含まれるため、亜鉛摂取には向かないと思えるかもしれません。しかし大豆発酵食品は発酵の過程でフィチン酸が減少することがわかっています。さらに消化管からの亜鉛吸収を増加させる可能性もあるとも考えられています。
日本人の食生活は亜鉛を含むミネラル分が不足しやすいです。ここで紹介した食材をメニューに取り入れながら、バランスの良い食事を心掛けましょう。
亜鉛が髪の毛に与える影響

(出典:(24)ホソカワミクロンが提唱する内外育毛ケア理論)(出典:(25)亜鉛欠乏症の診療指針2018)(出典:(26)男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版)(出典:(27)亜鉛とアゼラ酸によるヒト皮膚における5α-レダクターゼ活性の阻害)
髪の毛の80〜90%は「ケラチン」と呼ばれる18種類のアミノ酸が結合したタンパク質で構成されています。亜鉛はケラチンを合成するために必要とされ、髪の毛のインナーヘアケアに欠かせないミネラルの一つです。
また亜鉛は、男性型脱毛症(AGA)に対して良い影響を与えることがわかっています。AGAは男性ホルモンの「テストステロン」が活性度の高い「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変わり、男性ホルモン受容体と結びつくことで引き起こされる脱毛症です。
亜鉛はテストステロンからDHTへの変換を助ける「5α還元酵素」と呼ばれる酵素の働きを阻害する働きがあり、亜鉛を十分に摂取することで薄毛予防につながる可能性があります。
皮膚障害による脱毛症を防ぐためにも、亜鉛が不足しないよう注意が必要です。
亜鉛サプリを飲むタイミング

(出典:(28)亜鉛欠乏症の診療指針 2018)
亜鉛サプリを飲むタイミングは、食後がおすすめです。食事で摂ることの多い動物性たんぱく質やアミノ酸、ビタミンCなどは亜鉛の吸収を促進します。
また亜鉛の血中濃度が高くなるのは経口摂取後3時間以内なので、血中濃度をある程度保つためには一気に飲むのではなく、朝・昼・夜など数回に分けてバランスよく摂るといいでしょう。亜鉛欠乏症の治療においても、亜鉛は分けて投与されます。
亜鉛サプリの正しい摂り方と注意点

亜鉛サプリには正しい摂り方と注意点があります。これらを守ることできちんと効果が得られ、摂りすぎによる弊害も防げるでしょう。
水やぬるま湯で飲む
(出典:(29)亜鉛欠乏症の診療指針 2018)亜鉛サプリは水かぬるま湯で飲みましょう。他の飲料と一緒に飲むと、亜鉛の吸収が阻害される恐れがあります。
亜鉛の吸収を妨げるとされている飲み物は、乳製品やコーヒー、オレンジジュース、アルコールです。
また亜鉛サプリを飲む直前や飲んだ直後に上記の飲み物を摂ることも避けたほうがいいでしょう。亜鉛が体内に吸収されづらくなり、亜鉛不足が解消されない恐れがあります。
3ヶ月以上継続する
(出典:(30)味覚障害の診断と治療) (出典:(31)健康食品は医薬品ではありません)亜鉛サプリは3ヶ月以上は継続して飲みましょう。亜鉛サプリを摂りはじめてすぐに体に変化が現れることは考えにくいです。
味覚障害の治療には亜鉛の投薬治療が行われますが、医薬品を投与した場合でも、効果が現れるのは早くて3ヶ月ほどだとされています。
サプリメントは健康食品であり、病気の治癒効果は認められていません。そのため医薬品の亜鉛よりも早く効果が実感できることは考えにくいでしょう。
すぐに効果が出ないからとサプリの量を増やしたり、飲むことをやめてしまったりせず、決められた摂取量を守って、3ヶ月間は様子をみてください。
ビタミンCと一緒に摂る
(出典:(32)亜鉛欠乏症の診療指針 2018) (出典:(33)厚生労働省eJIM | ビタミンC)亜鉛はビタミンCと一緒に摂ることがおすすめです。ビタミンCは亜鉛の吸収を促進することがわかっています。
ビタミンCが豊富な食材は以下のとおりです。
- かんきつ類
- キウイ
- いちご
- ブロッコリー
- トマト
- 赤・緑ピーマン
ビタミンCもサプリメントで補うことができるので、食事で補いきれない場合は活用してみましょう。
1日の目安摂取量を守る
(出典:(34)厚生労働省eJIM | 亜鉛)亜鉛は1日の目安摂取量を守ることも大切です。過剰に摂ると食欲不振や嘔吐・下痢、吐き気や胃けいれんなどが起こる可能性があるので注意しましょう。
亜鉛の過剰摂取が長く続けば、免疫が低下したり善玉コレステロールが減ったりする恐れもあります。また亜鉛が銅の吸収を妨げることで、銅が不足してしまう可能性もあるでしょう。
亜鉛は不足すると健康に影響を与える栄養素ですが、摂りすぎも体に良くありません。サプリで補う場合も、過不足なく摂取するようにしましょう。
まとめ
体に必要な亜鉛の量はごくわずかですが、健康維持に欠かせない重要な栄養素です。またアンバランスな食生活で不足しやすく、亜鉛不足の日本人は増加傾向にあるとされています。
食生活を見なおし、毎日の食事から十分な亜鉛を摂取するのが理想的ですが、どうしても難しい場合は亜鉛サプリも活用してみましょう。サプリを使うときは用法・用量をしっかりと守り、亜鉛の吸収を助ける食材とともに飲むのがおすすめです。
健康な体を維持するためにも、過不足なく亜鉛を摂ることを意識してみましょう。
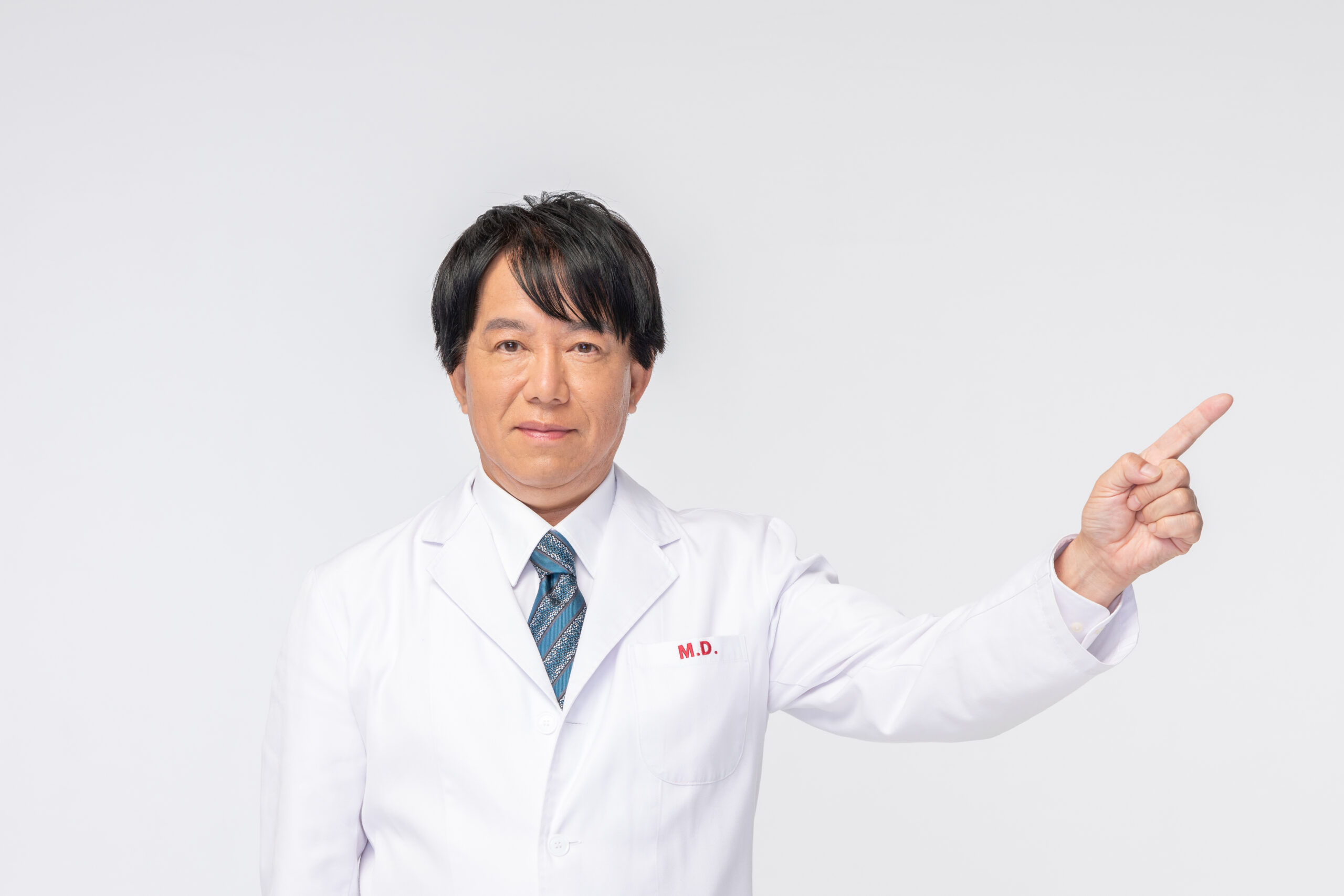
- 1).7).34).厚生労働省「統合医療」に係る情報発信等推進事業eJ.M
- 2).亜鉛栄養治療 6 巻(2015) 1 号
- 3).16).国立健康・栄養研究所「「健康食品」の安全性・有効性情報」
- 4).亜鉛栄養治療10巻2号 2020
- 5).亜鉛栄養治療7巻1号2016
- 6).Oregon State University
- 8).Oregon State University
- 10).昭和大学歯学部口腔病態診断科学講座口腔病理学部門
- 11).化学と教育 55巻11号 (2007年)
- 12).Vltarnins(Japan),82(10),539‐ 542(2008)
- 13).独立行政法人 農畜産業振興機構「畜産の情報 2017.9」
- 14).臨床研究センター 研究紹介
- 9).15).25).28).29).32).日本臨床栄養学会雑誌 第40巻 第2号 (2018)
- 17).文部科学省「日本食品標準成分表 魚介類」
- 18).文部科学省「日本食品標準成分表 豆類」
- 19).文部科学省「日本食品標準成分表 野菜類」
- 20).神戸学院大学 研究課題「米の亜鉛の栄養有効性の化学的・系統的解析」
- 21).農林水産省|消費者相談 過去の相談事例 穀類
- 22).日本醸造協会誌 第106巻12 号
- 23).日本型食生活の栄養学的検討(1)
- 24).The Micromeritics No.61(2018)84-87
- 26).日本皮膚科学会雑誌:127(13),2763-2777,2017(平成 29)
- 27).Br J Dermatol.1988 Nov;119(5):627-32.
- 30).日本耳鼻咽喉科学会会報/122 巻 (2019) 5 号p. 738-743
- 31).群馬県|ぐんま食の安全情報 vol.189 (2022.12)
- 33).厚生労働省eJIM | 「統合医療」情報発信サイト